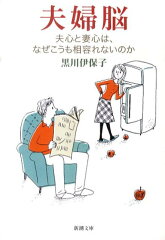「エコープラナーMRIによる安静時の脳活動における運動皮質の機能的連結」
「つるむ」という言葉があります。
おんなじ者同士、似たもの同士職場や教室で一緒になってグループを作って行動する、こういった行動はあちこちで見られると思うのですが、これはヒトの脳も同じようです。
これがどういうことかというとたとえば記憶に関係するような脳の部分というのは記憶に絡んで協調して行動するし、注意に関係するような脳の領域というのもやはり同じように協調して行動する。
こういった脳の「つるみ」を脳の機能的ネットワークと呼ぶのですが、この機能的ネットワークを見つけるためにはどうすればよいのでしょうか。
今日取り上げる論文はこの脳の機能的ネットワークの検出方法について調べたものです。
この「つるみ」を見つけるためには実際に記憶課題を行わせたり注意課題を行わせたりしてその時の脳活動を調べるのも一つの方法ですが、何もしていない時、ボーっとしている時の脳活動からでもそれぞれの機能的な「つるみ」を見つけることが出来ることが示されています。
|
|
【要旨】
エコープラナー法を用いて250ミリ秒毎で取られた512コースの安静時の脳活動画像を対象に研究を行った。手指の運動にともなって活動した領域を機能的MRIを用いて同定した。安静時の0.1Hz未満の低周波のゆらぎは機能的MRIで得られた手指の運動に関連する領域と強い相関を示していた。この結果から安静時の脳活動情報からも機能的ネットワークを検出できると考えられた。
参考URL:Functional connectivity in the motor cortex of resting human brain using echo-planar MRI.
コメント
これは例えばコーラスグループをパッと見ただけだとどこがアルトでどこがソプラノかというのは分からないけど
実際に歌を歌ってもらえば、この部分は同じパートを歌っているからおんなじグループだなというふうに理解は出来る。
でも歌を歌わせないでソプラノとアルトを区分けしてくださいという状況の時にどうすればよいかというと
これは練習の合間にざわざわしていいるのを考えて
同じパートの人はやはりおしゃべり声の声質も似ているし、同じパートの者同士ぺちゃくちゃおしゃべりする頻度も高いかもしれない、そういったことから、なにも歌わせなくてもある程度のグループ分けも出来る、そういうことなんだろうかというふうに理解しています。
とはいえ、この辺は非常に自信がなく決して丸受けせず読み流すくらいにしてももらえればと思うのですが
どなたか明るい方がいらしたらコメントいただけたらありがたいですm(_ _)mm(_ _)m